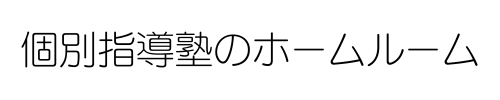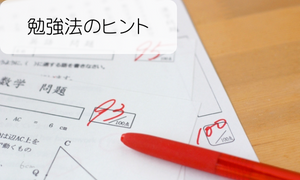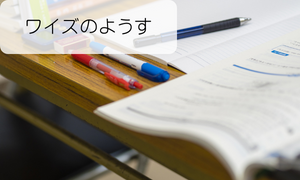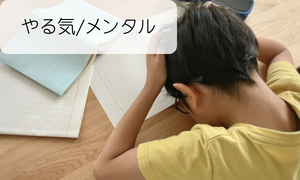年度最初の定期テストが近づいてきました。
当塾に通っている生徒の中学校では、6月中旬に実施されます。
テストに向けて上手に計画を立てて、実行したいですね。
でも一言で「計画を立てろ」と言われても、どうすれば良いか戸惑うことも事実。
- 定期テストの計画をどう立てたら良いかわかりません。
- 部活や学校行事、他の用事との両立はどうすれば良いのでしょうか。
- 計画に遅れが生じたら、やる気がなくなります。
気持ちはよくわかります。
私は計画を立てないとやる気が出ない方です。
年中計画を立てています。
- 定期テストの計画をどのように立てたら良いのか。
- 計画が頓挫しそうな時どうするか。

よしのせんせい と申します。
札幌で個別指導塾の代表講師をしています。
塾講師家庭教師歴29年。指導人数80名ほど。
中学受験・高校受験・大学受験指導をしてきました。
タイの中高一貫校で日本語講師をした経験があります。
計画を立てる手順
テスト範囲を正確に把握する。
まずはテスト範囲を正確に把握することです。
これは当たり前のことですよね。
でもたまに「テスト範囲表ある?」ときくと「えーっと、どこやったかな?」と言い出す生徒がいます。
困ります。
教科書、学校のワークのどこが範囲なのか、付箋を貼ったりして確認してください。

市販の問題集や塾のワークでの範囲を確認するのも良いと思いますが、教科書と学校のワークが優先です。
テスト範囲の表は、全体を俯瞰できるように表を作ることをお勧めします。
当塾では私が、大雑把ですが以下のような表を作っています。

勉強したページには❌や⭕️をつけて進捗をビジュアルで把握できるようにします。
達成感を味わうことができますし、モチベーションアップにつながります。
部活、行事、用事のある日を確認する。

テスト前2週間の間にも勉強だけでなく、行事や部活、家族の用事など、他にもやらなければならないことがあるでしょう。
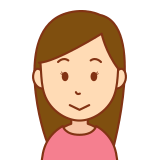
中2、中3は宿泊学習、修学旅行など旅行的行事が入ることがあります。

では、それらの行事をあらかじめ考慮して計画してください。
それらを無視して計画すると、その行事の時に計画が頓挫します。
テストまでの日数を計算し、1日どのくらい勉強すれば良いか割り振る。
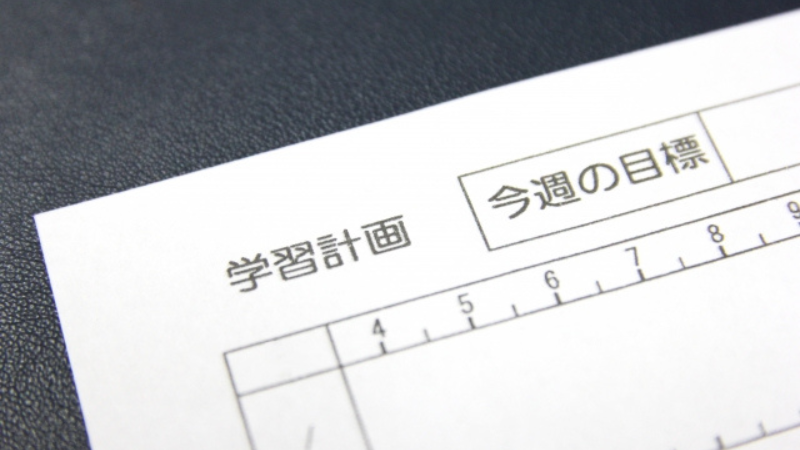
上の2つのことを踏まえて、1日どのくらいのペースで勉強すべきかを計算し、日毎の勉強内容を割り振っていきます。
行事の後などで体力が奪われ、あまり勉強できないことが予想されるなら、その日は軽めの勉強にする、得意単元など取り組みやすいものにしておく、など対策を立てておくことができます。

勉強を軽めにする計画、休息の計画も立てるわけですね。
そのかわり頑張って、たくさん勉強時間を確保できる日も計画しておきます。
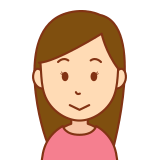
目標にすべき勉強量はどのくらいですか。2時間ですか。3時間ですか。
復習は1回で済むものではありません。
何度も繰り返さないと、脳内にインプットできませんね。
ときどき上記のような質問や「何回復習すれば良いのですか」という質問を受けますが、繰り返すべき回数や勉強時間は人によって、教科によって、目標によって異なってきます。
能力は、生徒によってまちまちなので、これだけやれ、とは断定できません。

「脳内にインプットできるまで」繰り返し勉強してください。
これが答えです。
計画倒れにならないために
進捗は毎日チェックする。
毎日の勉強も、勉強した内容(ページ)の確認も後回しにしないようにしましょう。

進捗の確認を怠ると、計画がどうでも良くなってきてしまいます。
日々進捗を確認して、危機感を持つこと、達成感を得ることはモチベーションを保つのに必要です。
上記のテスト範囲表を活用してください。
2週間の大まかな計画、1週間の細かな計画を立てる。

実行力がなく、いつも数日で計画通りいかなくなり、嫌になってしまう、ということはよくあります。
自信のない人は、細かい計画は2週間分ではなく1週間分だけ、あるいは5日だけ、など短めの計画にしておきましょう。
前半の1週間ほどの実行状況を見て後半の計画を立てるのです。
この方法だと、挫折感を軽減できます。
計画がうまくいかなくなったら、作り直せば良いのです。

投げやりにならず、頑張る気持ちを保てれば、勉強量・効率ともに維持できます。
計画の実行を諦めない。


計画が頓挫する時は大抵、計画作成の段階で失敗しています。
もともと無理がある計画だった、とか、進捗を俯瞰できないといった挫けやすい要素がある、といったことです。
上記の提案を吟味して、モチベーションが上がる計画を立ててみましょう。
楽しく計画してください。
まとめ
計画の立て方について提案してきましたが、実際に立てるのは生徒たちであるべきだと思います。
計画を立てることもまた勉強だと思うからです。
もちろん、どうしても計画が立てられない、という生徒には一から指導しますが、それでもその生徒の意見を使って計画を作成します。
適切な計画を立てるのは社会に出てからも必要なスキルです。
勉強でも、仕事でも、成功するためには計画がまず必要とされます。

「いきあたりばったり」は不安要素でしかありません。
人からの信頼を得るためにも大切ですね。
自分なりの計画の立て方、実行方法を確立することは非常に大切です。
一生モノのスキルになります。
以上、計画作成の参考になればと思い、これまでの経験と指導をまとめてみました。
ご参考になれば幸いです。