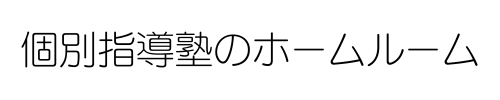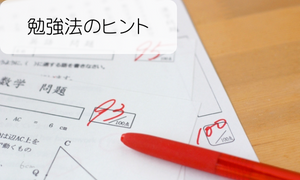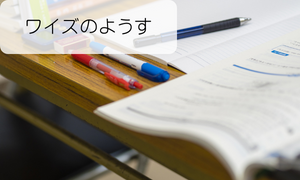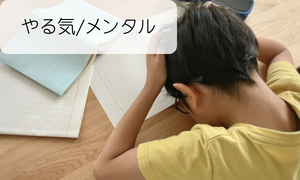テストの前になると「なぜこんなことを勉強しなければならないんだ!」という生徒の叫びをよく聞きます。
連立方程式なんて実生活では使わないのに、なぜ勉強しなければならないのか。
勉強や入試が嫌なあまり「来年、地球は爆発するんです!こんなことをしている場合ではない!」とまで言い出す人も。
20年以上この仕事を続けていますが、毎年恒例の「青年の主張」です。
地球爆発説はさておき「なぜ勉強しなければならないのか」という疑問には、大人もなかなかうまく答えられないことがありますね。
ただ、生活していて「もっと勉強しておけば良かった」と後悔するシーンが多いのも事実ですし、「勉強しなくて良かった」と思うことはほぼ皆無です。
そこでこの記事を作ってみました。
- なぜ勉強しなければならないのか。
- 実用性があるとは思えない知識をなぜ学ぶのか。
このテーマについては、なるほどと思える回答が世間にはたくさんあります。
以下は、私なりに考えたことです。
連立方程式など、中学生が学ぶ単元を引き合いに出します。
ご了承ください。

よしのせんせい と申します。
札幌で個別指導塾の代表講師をしています。
塾講師家庭教師歴29年。指導人数80名ほど。
中学受験・高校受験・大学受験指導をしてきました。
タイの中高一貫校で日本語講師をした経験があります。
勉強する理由
思考力の基礎トレーニングになるから。


スポーツを上手になろうと思ったら、基礎体力向上のためのトレーニングが必要ですよね。
ランニングをしたり、腕立て伏せや腹筋などの筋トレを行ったりします。
実際の試合中に腕立て伏せを行うことはまずありませんが、それでも必要なトレーニングです。
連立方程式を解く意義もこれに似ています。
思考力の基礎トレーニング、というわけです。
では具体的に、連立方程式を解けるようになるとどんな力が鍛えられるのでしょうか。
加減法や代入法を使いこなすということではありません。
1.問題を分析し、思考し、正しい答えを導き出す力。
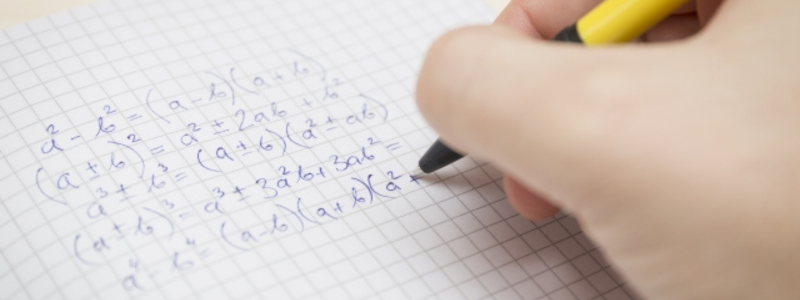
問題文を読んで、何を求めるべきなのか、どのようにしたら回答に至るのか、考えなくてはなりません。
この過程が大切です。
これは実生活で問題にぶつかった時に思考し、解決策を導き出すトレーニングになっています。

問題をろくに読まずに、短絡的に答えを出そうとする子は少なくありません。
実生活では問題の本質を理解していないがために、解決に苦労することはよくあります。
それを避けるためにもこのトレーニングは重要です。
2.わかりやすく自分の考えを説明する力。

数学の問題を解くには定義や定理、公式という根拠や共通の理解、客観的事実に基づいていることが必要です。
自分の好き嫌いや独自の感覚、主観的な意見は根拠にはなりません。
相手が納得できる説明ができなければなりません。
なぜその答えになるのか、回答した自分と回答を見る相手(採点者)双方が納得しなければなりません。
そのためのトレーニングです。

幼い子供は、泣いたり怒ったりして、自分の意思を通そうとします。
大人はそういうわけにはいきません。
感情ではなく思考力を働かせて、論理的に自分の意思を説明できなければ、相手は納得しませんね。
そのためのトレーニング、というわけです。
3.経験を活かす力。
数学だけではなく、他教科も出題には傾向があります。
パターンが決まっていて、この時はこのアプローチで解けば良い、とすぐに解法が閃くことがあります。
それは過去に、どこかの問題集やテストで解いた経験を活かしているわけです。
実生活でも、経験がモノをいうことがよくあります。
なんでも新鮮な気持ちで取り組むのも良いかもしれませんが、良きにつけ悪しきにつけ、経験を活かせるなら、問題解決の糸口が見つけやすいですよね。
例題を解いたり、たくさん問題を解いたりすることは、この力の訓練にもなっています。

こんなこと、当たり前じゃないか、と思われるかもしれません。
でも意外に、例題や模範回答を活かして解くことの出来ない子、多いんですよ。
可能性を探る機会となるから。


自分の興味のあることと自分の才能のあることは、必ずしも一致するわけではありません。
下手なのに好きな趣味、ってありますね。
歌を歌うことは大好きなんだけど、上手かいうと微妙、ということもあります。
反対に、非常に才能を感じるのに、本人はそれにあまり興味を示さない、ということもあります。
水泳が得意で大会に出ればいつも優勝、という子がいましたが、その子の将来の夢はオリンピックではなく意外にも電車の車掌さんでした。
ということは逆に、自分の興味のないことに自分の才能を活かせることがあり得ます。
好きなこと、興味があること、今のところ得意だと思えることだけに取り組んでいたら、自分の真の才能に気付かないかもしれません。
大変な思いをすることもあるかもしれませんが、学校の教育課程に沿って勉強していたら、自分の思わぬ才能に気づくこともあるのです。

それは「幸せな偶然」です。
確かに、どうしても好きになれないこと、関心が持てないこともあります。
でも実は、自分の関心のない世界を知る機会は、将来なかなか訪れません。
音楽に関心のない人が音楽を勉強する機会は、大人になったらなかなか訪れませんね。
学校に通い、勉強をしていたら、その機会が訪れるのです。
自分の才能、自分の可能性を知る機会、と考えてほしいです。
実行力のトレーニングになるから。
勉強していると、テストやレポートで結果を出すことが求められます。
そのために必要なことがあります。
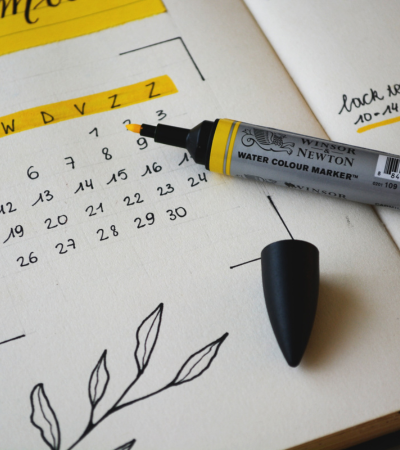

良い結果を出すには、計画とセルフコントロールが必要です。
テストの日程やレポートの提出期限が決まったら、それまでにいつ、何をすれば良いのか、計画を立てますね。
そしてその間は、セルフコントロールが必要です。
いつものように、なんでもわがままに暮らしていたら、時間がなくなります。
自分の好きなことをセーブして、勉強に時間を費やさなくてはなりません。

良い結果を得るには、犠牲が求められます。
勉強することは、それを学ぶ機会となるのです。
さらに、次のことを理解するのも意義のあることです。

頑張っても必ずしも良い結果が出るとは限らない。
ささいな失敗でも、異常なほど落ち込んだり、怒り出したり、拗ねたりする子がいます。
バツが付くだけでいじけてしまいます。
でも、いつも全問正解、100点しか取ったことのない人間なんて、人間ではありません。
人生はトライアンドエラーの繰り返しです。
失敗のたびに機嫌を悪くしていたら、暗くなってしまいます。
問題は、失敗した後にどうするか、を考えることです。
失敗を分析し、次に成功するにはどうするかを前向きに検討する。
この習慣が大切です。
失敗した自分を責めすぎず、反省を生かし、改善を考えていく。
それが成長につながります。
まとめ
勉強する意義は、目標が定まっている人は受け入れやすいものです。
資格を取る、憧れの学校に入りたい、など明確な目標のある人は何も言わなくても勉強します。
目標がはっきりしない中で勉強を強いられるというのは確かに辛いことです。
それは理解したいです。

明確な目標がある人も、目標がない人も、勉強、というより、
上に提案した思考力や実行力などは必要ではないでしょうか。
生徒たちに勉強の理由を尋ねられた時、わたしはこの記事の内容をよく話します。
ご参考になれば幸いです。